|

|
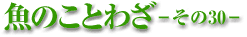
---アユ---
海とその生物にまつわる諺や格言についてお話ししましょう。
今回のテーマはアユ(サケ目アユ科アユ属)です。
アユの成魚は川で生活し、全長は10~30cmになります。秋に成熟した親は、河川の中流から下流域へ移動して産卵し、仔稚魚は一時的に海で生活した後、翌年の春から初夏にかけ河川を遡上します。このような回遊は「両側回遊」(りょうそくかいゆう)と呼ばれます。ただし琵琶湖などに生息する湖沼陸封型(いわゆるコアユ)は、海の代わりに湖を利用します。
アユは、縄張りを持つ習性を利用した「友釣り」がポピュラーであり、全国河川のアユ釣り解禁日には、多くの釣りファンが河川に集まります。 |
|
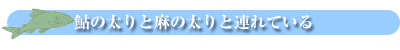
アユと麻は、目に見えて大きくなる、という石川県地方の言葉。アユはアユ科の一年魚、麻はクワ科の一年草。一年で使命を達成するためには、ボヤボヤしておられない。春に生じて秋には子孫を残し短い一生を終えるのである。
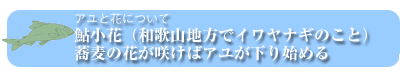
 アユは清流の魚であるが、河口で生まれて海で育ち、清流で「成鮎」となり秋には「落ち鮎」となって川を下り、産卵をして短い一生を終える年魚。イワヤナギが咲き出すと、若アユが遡上し始める。初夏の到来。秋に蕎麦の花が咲く頃、腹子を抱いた鮎が産卵のため、河口に向かうこと。紀伊地方の言葉。 アユは清流の魚であるが、河口で生まれて海で育ち、清流で「成鮎」となり秋には「落ち鮎」となって川を下り、産卵をして短い一生を終える年魚。イワヤナギが咲き出すと、若アユが遡上し始める。初夏の到来。秋に蕎麦の花が咲く頃、腹子を抱いた鮎が産卵のため、河口に向かうこと。紀伊地方の言葉。
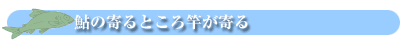
アユは釣り人が集まっている場所で釣れば、まずあぶれることがないといわれる。大勢が知らず知らずに集まるところは、やはり良いポイント。釣りは一に場所である。
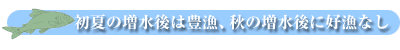
アユ釣りに関する言葉。春の若鮎は上流の清流域を目指して遡上するが、大雨などの増水で押し戻されても再び遡り、「差し返し鮎」「差し戻し鮎」と呼ばれて、また釣れるようになる。しかし、秋は産卵期を迎えて「落ち鮎」となり、川を下るので、このときに増水があると、そのまま下ってしまい二度ともどってこない。

アユ・アンコウ・タイの美味な筆頭産地。岐阜のアユは長良川、水戸のアンコウは千葉県銚子沖~福島県常磐沖、明石のタイは徳島県鳴門海峡~兵庫県明石で捕れる。
二階堂清風編著「釣りと魚のことわざ辞典」東京堂出版より転載。
| CO2が海洋生物におよぼす影響(2) |
マダイの二酸化炭素(CO2)耐性を調べるために、卵から稚魚まで成長を追ってCO2影響実験を行いました。その結果、マダイのCO2耐性は一度高くなったあと再び低くなる傾向が認められ、発育段階によって異なることが分かりました。下図は成長に伴うマダイの半数致死CO2レベルを示しており、CO2耐性の指標となります。このマダイの実験は海生研ニュースNo.83で詳しく紹介しています。
(中央研究所 海洋生物グループ 吉川 貴志)
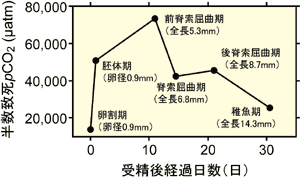
マダイの成長に伴う半数致死CO2分圧(pCO2)の変化
(自然海水のpCO2は約380μatm)
|
|
|