|

|
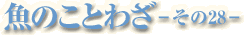
---コノシロ---
海とその生物にまつわる諺や格言についてお話ししましょう。
今回のテーマはコノシロ(ニシン目ニシン科ドロクイ亜科コノシロ属)です。コノシロには鮗と■の字が使われますが、■はサンマを指すこともあります。
コノシロは成長に応じて呼び名が変わりますが、小振りのものほど珍重され、大きくなるほど値段は下がっていきます。関東では、5~6センチのものをシンコ(新子)、7~10センチのものをコハダ(小鰭)、12から13、14センチをナカズミ、それ以上をコノシロ(鮗、■)と呼びます。関西ではコノシロの幼魚をツナシ(▲)と呼びます。
名の由来としては、国司に一人娘を召されそうになった親が、娘は死んだと偽って、焼く臭いが人を焼く臭いに似る魚を棺に詰めて焼くことで難を逃れたことから「子の代」と呼ぶようになったという説があり、コノシロが殆ど酢漬けなどで食され、焼くことが少ないのは、この臭いのためと「この城を焼く」ことを武士が嫌ったためともいわれます。
■=魚ヘンに祭
▲=魚ヘンに制
|
|
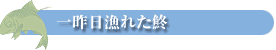
阪神地方でイキのよくないもの(魚)の形容。小魚、特にコノシロは新鮮さが命。コノシロは死後直ぐに味が失せることからこの言葉が生まれた。
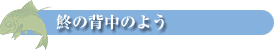
コノシロの背中には光沢があり、美しいところから、綿布や衣服に光沢があることをいう。
コノシロに限らず「光り物」(アジ・サバなど、皮付きの鮨種の総称)と称する魚の背には、青い光沢があって美しい。
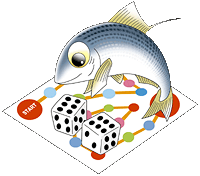 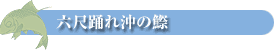
双六で賽の目が六と出たときにいう言葉遊び。コノシロはボラのように沖に出ることはなく、六尺も飛び跳ねることもあり得ない。賽の目は六が最高、この六を六尺に掛け、更に滅多にないことを掛けた洒落?
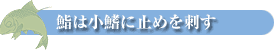
「鰻は蒲焼に止めを刺す」をもじったものであろうか。鮨の中でコハダ(コノシロの幼魚)が一番飽きが来ない。また鮨の最後に食べるとよい、ということ。

明治時代の魚屋言葉(隠語)。「兄」は年を取っている、というところから転じて、古くなった魚のこと。反対は「弟」で新鮮な魚を指す。同じように「お泊まり」は前日仕入れた魚の売れ残り。明治時代の鮨屋のカウンターのネタは弟、出前のネタは兄かお泊まりだそうで、同じ値段だが、出前料は兄がまかなっていたという。
二階堂清風編著「釣りと魚のことわざ辞典」東京堂出版より転載。
| 魚の繁殖生態(7) |
ニベの繁殖行動を産卵期の6~8月に調査しました。産卵は21時~0時に行われ、その多くは22時頃に集中しました。この時刻前になると、水槽からはカエルが鳴くような音が聞こえてきました。その音は始め小さく、発音間隔は空いていますが、しばらくして、雌が産卵する頃合いになると、大きい音が頻繁に聞かれるようになりました。この音は、ニベの地方名であるグチ(愚痴)ではなく、産卵期の雄の求愛音のようです。

| ニベの発音筋にみられた雌雄差(薄ピンク色の発音筋は雄で大きく、雌では未発達)。発音筋が鰾(うきぶくろ)をとりまき、その震動を鰾で共鳴させて音を出す機構になっています。 |
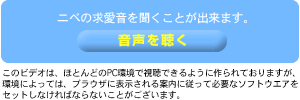
|
|