|

|
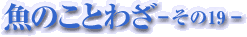
---コチ---
海とその生物にまつわる諺や格言についてお話しましょう。
今回のテーマはコチ(カサゴ目、コチ科)です。
コチは、夏が旬の魚で、7~8月が脂がのって美味です。頭が押しつぶされたように扁平で見た目はよくありませんが、味はフグ並みと言われております。
体長20cm以下の多くはオス、50cm以上の全てはメスでこの間に性転換をする魚として知られております。 |
|
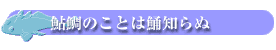
「相対のことはこちゃ知らぬ」の言葉に、アユ・タイ・コチの魚名を置き換えて洒落言葉にしたもの。当人同士が差し向かいで決めたことはあずかり知らぬ。予め相談のないことで、後にゴタゴタがおきても、こちらには何の責任もない、と突っぱねるときに言う言葉。相対は、一般には売り手と買い手をいうことが多い。アユ・タイ・コチに代って、アユ・タイ・コイを当てるものもあるが、コイは恋。男女の関係をいうのであろうか。
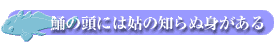
一見、骨ばかりに見えるコチにも身があり、特に頬肉は量が少ないものの旨いところ。一般に、魚の目玉・頬肉・顎の部分は美味。また、人が捨てるようなものにも、よく探せば価値のあるものが見出せることの例えにもいう。
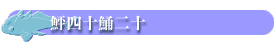
ヒラメやコチ釣りでは生き餌(主にイワシ)を使うので、食い込みに時間が掛かる。そこで最初の魚信(アタリ)から暫く待って、十分呑み込んだ頃合を読んで合わせる。早合わせをすると餌がすっぽ抜けしてしまう。そのコツを説いた言葉だが、実際には「鮃十五鯒五」くらいの間合でいい。
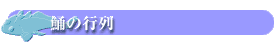
何尾ものコチが一、二列縦隊になって行儀よく並び泳ぐさまをいう。勝手気ままな「水母(クラゲ)の行列」とは対照的である。

二階堂清風編著「釣りと魚のことわざ辞典」東京堂出版より転載。
| 実験魚を育てる(1) |
海生研では、温度などの様々な環境要因の変化に対する海生生物の反応を明らかにすることを目的に、各種の実験を行っています。対象となる生物は実験目的により異なり、発育段階も卵や稚魚、成魚などと多様です。実験に使用する魚類のほとんどは海生研で飼育しており、それらは各種の実験の要請にいつでも対応できるように管理されています。水産有用種のマダイやヒラメなどをはじめ約20種の海水魚については、繁殖技術が確立されています。これらの技術を種の保存のために活用し、絶滅危惧種とされるアオギスも繁殖可能としました。

受精卵から育てたアオギス(全長約20cm)
黄色の腹鰭、臀鰭が大きな特徴(円内)
|
|