|
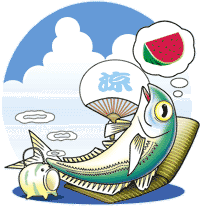
|
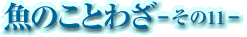
---アジ---
海とその生物にまつわる諺や格言についてお話しましょう。
今回のテーマはアジ(鯵)です。
世界でアジ科の魚は140種ほど、日本では約50種が生息しています。
「味とは、アジなり」といわれるように、この魚が語源になったといわれています。
日本でアジといえばマアジをいい、日本の各地沿岸に分布し、沿岸から沖合にかけての中・底層域に群をつくり、薄明時から薄暮時までに活動する昼行性の魚です。
イワシ、シラス、イカ、甲殻類などをよく食べます。
|
|
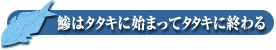
「鯵は生でよし、干してよし、焼いてよし、漬けてよし」。鮨も旨いがタタキが身上という。このタタキ、元を質せば漁師の船上即席料理で、「手こね鮨」に似たような由来。それだけに新鮮さが味を左右する。この言葉は「釣りは鮒に始まって鮒に終わる」をもじったものであろう。
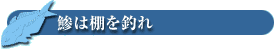
アジ釣りには重いオモリが有利。普通、アジの上層にサバがいて、オモリが軽いと餌がアジの棚に届く前にサバが横取りしてしまい、アジを釣りに行ったのに釣れるはサバばかり。重いオモリで一気にアジの棚に餌を落としてやるのがコツ。ということは、サバよりアジの方が魚格が上?
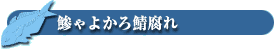
 アジは要らない、サバも腐っているから欲しくない。転じて、どれもこれも駄目で、相手にする値打ちがないというあざけりの言葉<長崎地方の諺>。 アジは要らない、サバも腐っているから欲しくない。転じて、どれもこれも駄目で、相手にする値打ちがないというあざけりの言葉<長崎地方の諺>。
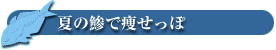
痩せた人を例えていう。アジそのものは夏痩せしないが、夏になると小鯵が出回るからであろうか。「鯵は味」で一年中旨い魚。
二階堂清風編著「釣りと魚のことわざ辞典」東京堂出版より転載。
| 貝類の温度耐性<2> |
海生研では、貝類について様々な試験研究を行っています。浅い海で岩などに付着して生活するマガキやアコヤガイなどの二枚貝は、環境変化を受けやすい生物の一つと考えられます。
図は、アコヤガイの高温に対する耐性を卵から殻長60mmの成貝まで調べた結果です。横軸は受精後の経過日数、縦軸は半数が死亡する温度です。受精後まもない卵の時期には高温に弱いこと、殻が形成されると高温に強くなりますが、発育が進むにつれて高温耐性が徐々に低下することがわかりました。
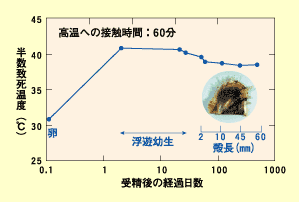
|
|